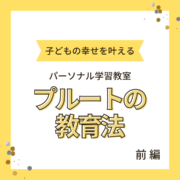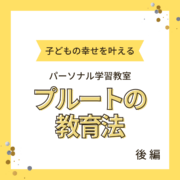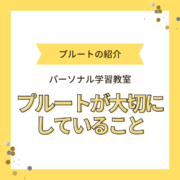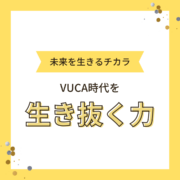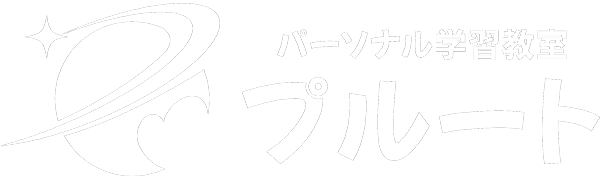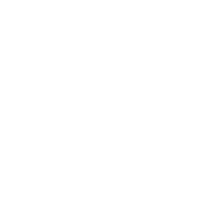子どもにどう伝える? 勉強する本当の理由
なぜ、勉強しなきゃいけないの?
「うちの子、なかなか勉強に集中しないんです…」
「どうして勉強しなきゃいけないの?」と、子どもに聞かれ、答えに困った。
こんな悩みを持ったこと、ありませんか?
私も教員時代、子どもたちに「なんで勉強しなきゃいけないの?」と、数え切れないほど質問されました。
勉強が嫌いだったり、興味を持てなかったりする子どもたち。そんな彼らに、勉強の本当の意味や価値を伝えるのは難しいですよね。
では、どう伝えたらいいのでしょうか?
この記事では、なぜ勉強が子どもにとって大切なのか、その本当の理由について探っていきます。ただ単に「いい成績を取るため」ではない、もっと深いところにある価値に気づけば、子どもたちの学ぶ姿勢も変わるかもしれません。
なぜ、子どもたちは勉強に興味を失うのか?
まず、どうして多くの子どもたちが勉強に対する意欲を失ってしまうのか、考えてみましょう。具体的には、次のような理由が挙げられます。
学んだことが身近に感じられない
小学校低学年のころは、学んだことが生活にすぐ役立つことが多いですよね。たとえば、国語の授業では日常で使う言葉や漢字を覚えたり、算数ではお買い物に使える計算を学んだりします。このように、勉強が「生活の一部」として感じられると、子どもたちは自然と楽しく学べるものです。
しかし、学年が上がるにつれて、学ぶ内容が次第に抽象的になり、生活との結びつきが見えにくくなります。たとえば、「三角関数を学んで、何に使うんだろう?」という疑問が出てきますよね。これが、勉強に対する意欲を削いでしまう一因なのです。
「自分が学んだことが、自分の生活に役立つ」という実感が得られないと、意欲は低下してしまうのです。
(でも、実はナビゲーションシステムやデジタル信号処理には三角関数が欠かせません。もしも、あなたがこれらの技術に携わる仕事に就くなら、きっと主体的に三角関数を学ぶでしょう)
学力向上が目的化してしまう
受験勉強やテストの点数が強調されると、子どもたちにとって勉強は「点数を取るためのもの」になりがちです。このように学力向上が主な目的になると、勉強そのものの楽しさや意義が見えにくくなります。子どもたちは「なぜこれをやらなきゃいけないの?」という疑問を抱え、勉強への意欲を失うことも。
今の社会では、知識だけでなく、それをどう活用するか、柔軟な思考力がますます求められています。つまり、「勉強はなぜ大切なのか」を、もっと深く考えることが必要なんです。
(詳しくは過去の記事「未来を切り拓く力を育む〜子どもの幸せを叶えるプルートの教育法」をご覧ください)
勉強の本当の意義=自分を磨くための道具
では、勉強はただの「テスト対策」や「知識の詰め込み」だけなのでしょうか?
実は、もっと大切な意義があるんです。それは、「勉強は自分を磨くための道具である」ということ。これがわかると、勉強に対する見方がガラッと変わります。
今、教育の現場では「非認知能力」を育てることが重要視されています。非認知能力とは、社会的スキルや感情的知性、自己制御、好奇心、そして逆境を乗り越える力(レジリエンス)などです。これらは学力とは異なる面で、子どもの成功や幸福に深く関わっています。
(詳しくは過去の記事「非認知能力が未来を切り拓く」をご覧ください)
勉強は、こうした非認知能力を育む最高の「道具」でもあるんです。具体的には、以下のような力が自然に身についていきます。
自己管理能力
勉強では、計画を立て、それを実行することが必要です。たとえば、毎日少しずつ宿題をこなすことで、自己管理能力が磨かれます。このスキルは、大人になってからも仕事や生活のあらゆる場面で役立ちます。
忍耐力とレジリエンス
特に受験勉強では、長期間の努力が求められます。途中で失敗や挫折を経験することもありますが、これらを乗り越えることで忍耐力やレジリエンスが育まれます。これらの力は、将来どんな困難に直面しても乗り越えるための原動力になります。
問題解決能力
勉強、特に数学や理科では、問題解決のプロセスが重視されます。試行錯誤しながら答えを導き出すことで、論理的思考力や問題解決能力が養われます。この能力は、学問だけでなく、日常生活や職場でも非常に役立つものです。
自己効力感
目標に向かって努力し、それを達成することで、自分の能力に対する信頼感が高まります。これが、自己効力感です。自己効力感は、あらゆる挑戦に対して前向きに取り組む姿勢を育てる原動力となります。
このように、勉強は学力向上が主目的ではあるものの、その過程で多くの非認知能力が自然に育まれます。
では、なぜ非認知能力を育てるにあたって勉強が重要なのでしょうか?
その答えは、勉強が非認知能力を最も効率的に育てる手段だからです。
確かに、スポーツや趣味を通じても非認知能力は育ちます。でも、サッカーを例に考えてみてください。サッカーをするには広いフィールド、ボールやゴール、そしてチームの仲間たちが必要です。さらに、天候にも左右されます。
一方で、勉強に必要なのは、ほんの少しのスペースと簡単な道具だけ。机一つ、鉛筆とノート、それに教科書があれば、すぐに始められます。勉強は一人でも取り組めますし、天気も関係ありません。
さらに、義務教育の期間中は毎日学校に通って勉強することが保障されています。そして、大人になってからも、やる気さえあればいつでも勉強を続けられるのです。勉強はいつでもどこでもできる、身近で強力な「自分を成長させる道具」なんです。
勉強の価値を子どもたちに伝える方法
これらの「勉強がもたらす力」を、ぜひ子どもたちにも伝えてみてください。ただし、「勉強しなさい」と命令するだけではなく、「どうして勉強が大事なのか」「どんな力が身についているのか」を、日常の中で一緒に考えてみることが大切です。
たとえば、スポーツが好きな子どもなら、スポーツを通じて学んだことと同じように、勉強でも自分を成長させられることを伝えてみるのも一つの方法です。勉強は特別な道具がなくても、どこでも取り組める活動ですし、その結果として身につく力は一生の財産となります。
子どもが勉強に取り組む中で、非認知能力を発揮したり、その成長を感じられたりする場面に出会ったら、すかさず褒めることも忘れてはいけません。
勉強の本当の価値を見つけることで、未来が変わる
プルートでは、子どもたちが勉強を通して、非認知能力を発揮し、伸ばしていくサポートを行っています。非認知能力は大人になってからも役に立つ重要なものです。
もし、勉強の本当の価値を理解すれば、子どもたちの学びに対する姿勢が変わるかもしれません。親や教師がその価値を伝え、子どもたちが自分の成長を実感できるようサポートすることで、学び続ける力が養われます。そして、それが子どもたちの未来を明るく切り開く力となります。
勉強を通じて、自分を磨く道具としての価値を見出し、未来への可能性を広げていきましょう。
まとめ
・勉強が生活に役立つという実感が得られない場合や点数アップだけが目的になっている場合、意欲が低下してしまう要因になります。
・勉強は自分を磨くための道具であること、勉強を使って様々な力を身につけることで、自分を成長させることができます。
・子どもに「勉強がもたらす力」を伝えると同時に、日常の中で「勉強によってどんな力が身に付いているか」を子どもと一緒に考えてみることが大切です。