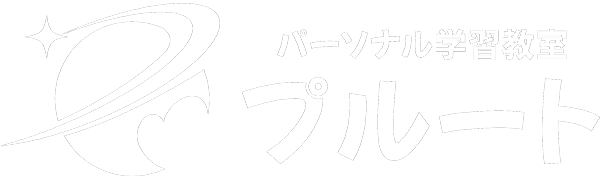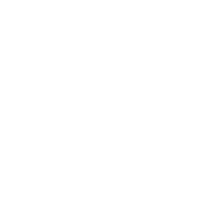ただ努力するだけじゃダメ!記憶を定着させる科学的勉強法
「ただ努力するだけじゃダメ!記憶を定着させる科学的勉強法」
「たくさん勉強しているのに、成果が出ない…」
「繰り返し練習したのに、なかなか覚えられない…」
こんなふうに、一生懸命頑張ったのに思うような成果が得られず、やる気がなくなった経験はありませんか?自分の課題を克服しようと努力するのは素晴らしいことですが、もしその努力が実を結ばないと感じるなら、勉強法を見直すタイミングかもしれません。
よくある勉強法の落とし穴
学校では、たくさんの学習内容が教えられますが、「どう学ぶか」という勉強のやり方自体が教えられることは少ないです。そのため、受験生や社会人になると、どうしても自己流で勉強を続けてしまいがちです。しかし、効果的な方法で学ばないと、記憶の定着率が下がり、学習効率も低くなってしまいます。そこで今回は、科学的に裏付けられた、学んだことを確実に記憶に残すための効果的な勉強法をご紹介します。
まず、実はあまり効果が高くない、よくある勉強法について見ていきましょう。多くの人が「これが勉強だ」と信じている方法の中には、実は気合や根気に頼りすぎて、効率的に知識を吸収しにくいものもあります。そのデメリットを一緒に確認していきましょう。
① 繰り返し書いたり読んだりして覚える
テキストを何度も繰り返し勉強したり、漢字を覚えるために何度も書いて練習する。誰しも一度は経験したことがある勉強法ではないでしょうか?確かに、記憶を定着させるために「繰り返す」という方法には一定の効果があります。ただし、ただひたすら意味もなく繰り返すだけでは、思ったような成果が得られないことも多いです。時間をかけても結果が出ないと感じている場合、この点を見直す必要があるかもしれません。
② ハイライトをする
テキストの重要な部分に線を引いたり、蛍光ペンでマークをしたりするのも、視覚的に「勉強している」という実感が得られる方法です。しかし、アメリカの研究では、ハイライトをすることが学習成果にほとんど影響を与えないと報告されています。さらに、どの部分が重要かを自分で判断する必要があるため、実際にはこの方法が難しく、効果的とは言い難い場合もあります。
このように、多くの人が行いがちな勉強法であっても、必ずしも効果的ではないことが教育現場ではいまだに多く見受けられます。「覚えるまで繰り返す」といった根性論に頼る方法や、ハイライトを引く方法も、効率が悪く、成果に結びつきにくいのです。
どんなに工夫した勉強法でも、成果が出なければ意欲を低下させてしまいます。では、どうすれば効果的に学べるのでしょうか?ここからは、具体的な勉強法をご紹介していきます。
記憶定着率が上がる効果的な勉強法
記憶の定着を高めるための大きなポイントは、ただ根気に頼るのではなく、脳をしっかり働かせることにあります。これは、脳をアクティブ(能動的)な状態にすることとも言えます。逆に、脳を受動的な状態にさせる勉強法は、効果が薄くなってしまいます。
先ほど挙げた効果が薄い勉強法を振り返ってみましょう。「読んで覚えようとする」学習は、一見勉強しているように思えますが、情報をインプットするだけでは脳はあまり活発に働きません。また、「繰り返し書いて覚える」「ハイライトをする」などの方法も、頭を使わず機械的に手を動かせてしまうため、脳の働きが鈍くなり、記憶の定着が不十分になりがちです。
では、脳をアクティブな状態に保ちながら効率的に学ぶには、どのような方法が効果的なのでしょうか?以下に、特に有効な2つのポイントを紹介します。
① アクティブリコール
アクティブリコールとは、学んだ内容を能動的に思い出す勉強法です。簡単に言えば、インプットした知識を自分で引き出し、思い出すことです。多くの人は、読書や講義などのインプットに偏りがちですが、実際にはアウトプットすることで脳が活性化し、記憶がより定着しやすくなります。実際、「勉強とは思い出すことだ」と言われるほど、この方法は効果が高いとされています。
科学雑誌『サイエンス』に掲載された研究では、80人の大学生を4つのグループに分けて学習効果を比較しました。「1回だけ勉強するグループ」「テキストを繰り返し読むグループ」「概念マップを使って勉強するグループ」「学んだ内容を再現する(アクティブリコール)グループ」のそれぞれで、1週間後のテスト結果を見たところ、アクティブリコールを行ったグループが最も高い成果を上げたのです。
さらに、アクティブリコールで覚えた知識は、時間が経っても記憶に定着しやすいことも確認されています。
アクティブリコールの効果的な学習のポイントは、インプットよりもアウトプットを重視することです。理想的なインプットとアウトプットの比率は、3:7と言われています。脳から記憶を引き出すアウトプットを多く取り入れることで、脳を能動的に働かせ、記憶定着を大いに助けるのです。
② 間隔反復学習法
間隔反復学習法は、「分散学習」とも呼ばれ、一度学んだ内容を時間を置いて何度も復習する方法です。これは、ドイツの心理学者エビングハウスが提唱した「忘却曲線」の理論に基づいています。この理論によれば、人は一度学んだことを1日後には約74%、1週間後には約76%、そして1ヶ月後には約79%も忘れてしまうとされています。
しかし、間隔を空けて繰り返し復習することで、この忘却のスピードを緩やかにすることができるとも示されています。同じ内容を何度も学ぶのではなく、間をあけることで脳に刺激を与え、より長く記憶に残りやすくなるのです。
ここから分かるのは、学習内容を一度にまとめて勉強するよりも、間隔をあけて少しずつ学ぶ方が記憶が定着しやすいということです。アメリカのスピッツァーがアイオワ州で行った実験では、間隔をあけて学習を繰り返すことの効果が明確に示されています。この実験では、科学知識の習得における迅速な効果も実証されました。
具体的には、3600人の6年生を対象に、同じ英単語を一度にまとめて勉強するグループと、2回に分けて学習するグループの成果を比較しました。どちらのグループも合計の勉強時間は同じだったにもかかわらず、5週間後に行われたテストでは、間隔をあけて学習したグループの方が成績が優れていたという結果が出ています。
また別の研究でも、1日で一気に勉強することは短期的な記憶には効果があるものの、長期的に記憶を定着させるには間隔反復学習が有効であることが実証されています。
これらの結果から、長期的な記憶定着を目指すなら、一夜漬けのような方法ではなく、定期的に繰り返し学ぶことが必要だとわかります。さらに、その繰り返し学習は、インプットに偏るのではなく、アウトプットを重視して脳をアクティブに(能動的に)働かせることが重要です。
アクティブリコールと間隔反復学習を組み合わせた勉強法では、知識に何度も触れることで脳がその重要性を認識し、記憶が定着しやすくなります。さらに、思い出せなかった部分は自分の弱点を明確にする手がかりとなり、効率的に学び直すチャンスを得ることができるため、非常に効果的な学習方法として活用できます。
プルートの学び
磐田市中泉にあるプルートでは、科学的根拠に基づいた効果的な学習法や学習環境を整え、子どもたちの学びを全力でサポートしています。それぞれの学習方法がどのような効果をもたらすのかをしっかりと示すことで、子どもたちは自ら納得し、自分の課題に応じた最適な学習方法を選び、主体的に課題解決に取り組むことができるようになります。
また、教室の見学や体験授業も実施しております。学習に関するご相談も随時承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。