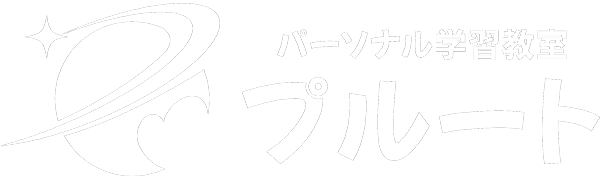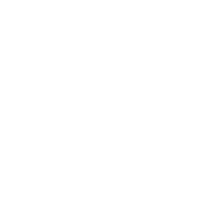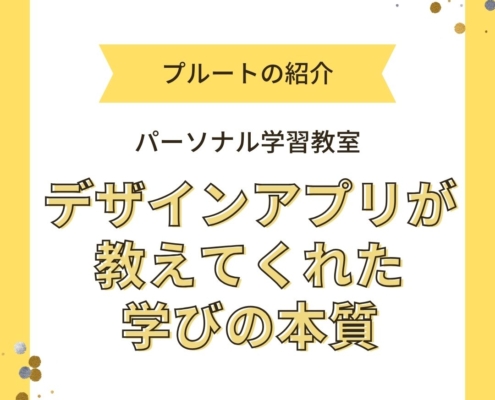
デザインアプリが教えてくれた、学びの本質
ICTアプリによる、学びの本質
子どもたちが帰ってくるランドセルの中には、皆タブレットが入っています。 子どもたちのタブレット使用の様子を見ていて、学習へのICT導入については、今もなお考え方に大きな温度差があると感じています。 (単なる重たい連絡帳になっているだけの子も…) 保護者の方や教育現場の中でも、「便利そうだけれど不安」「本当に必要なのだろうか」と迷われている方は少なくありません。 私自身、教員時代にはICT主任として機器活用を先行して行い、先生方への研修にも関わってきました。その経験から、ICT導入に慎重な立場の方が抱きやすい不安は、大きく次のようなものだと感じています。 ・使っているとトラブルが起きやすく、対応できない (ちなみに私は、ICTは「いつも、ちょっと、トラブル」の略だと思っています…
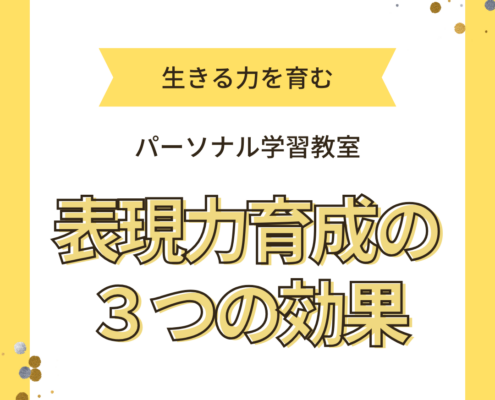
表現力を育むことで得られる3つの効果
表現力を育むことで得られる3つの効果
今回は表現力を育むことでどんなことが得られるのかについて考えます。「表現力」は、学校の授業だけでなく、社会に出てからも必要なスキルです。特に今回、取り上げる表現力を育むことで得られる3つの効果は子どもの可能性をさらに大きく広げます。
ポイント①:論理的思考力の向上
自分を表現するためには、自分の意見や気持ちをしっかり伝えられるようになることが必要です。そのためには「何をどう伝えたら良いか」を考えますよね。このプロセスが論理的思考力を鍛えることにつながっていきます。作文などで、「結論は何か」、「なぜそう言えるのか」、そして自分が考えたことを「どのように伝えると相手が理解しやすいか」を考える経験を重ねることによって、物事を整理し、順序立てて結論を導き出す力が身につきます。 この論理的思考力が身につくと学校の授業にも役立ちます。問題を解く際に「なぜこの答えになるのか」を説明できるようになります。そうすることで、より深い理解が得られ、学力向上にもつながります。
ポイント②コミュニケーションスキルの習得
表現力を高めることで、コミュニケーションスキルの習得につながります。このスキルは、学校生活の中でも役立ちます。例えば、プレゼンテーションやグループディスカッションで意見を出し合ったり、友達や先生との会話で自分の意見をきちんと伝えたりすることができると周囲から信頼も得やすくなるでしょう。 自分の考えを分かりやすく表現する力を身につけていくと話し合いもスムーズにできるので、友達とのトラブルなどを未然に防ぎやすくなります。 さらに、コミュニケーションスキルは成長するにつれて、チームワークやリーダーシップの向上にも発展していきます。相手の話をしっかり聞き、自分の意見を適切に表現できる力は社会に出てからも必要です。この基礎を小学生のうちから養うことが、将来の大きな財産になります。
ポイント③ …
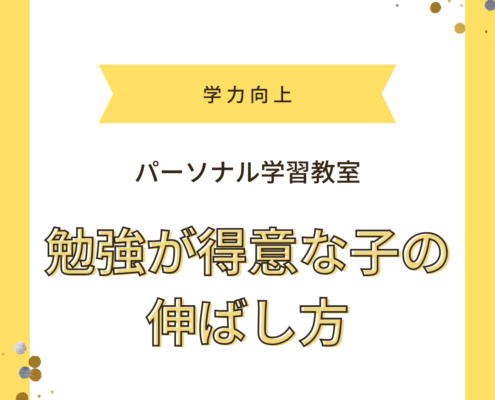
勉強が得意な子の伸ばし方
勉強が得意な子の伸ばし方
磐田市中泉で学童保育型学習塾プルートを運営している塾長の藤田です。 「子どもが勉強にどれくらい取り組めているのか」、親として気になるポイントですよね。特に、学校のテストの点数や成績が良ければ安心しがちですが、本当にそれで大丈夫なのかと悩むこともあるかと思います。 勉強が得意な子であっても、「このまま現状に満足していいのか?」「もっと力を伸ばせる方法があるのではないか?」と感じることも多いはずです。 勉強が得意なお子さんは、どの学校にも一定数います。でも、学校で充分活躍できるレベルであれば、それ以上に力を伸ばす必要はないのでしょうか? どんなお子さんでも、常に成長していくことを意識したいものです。今の状況に満足することは、自己肯定感の高さを示す反面、自分の限界を決めてしまうことにもつながるかもしれません。また、学校の勉強は社会に出るための基礎力であり、それがそのまま社会で求められる力とは限りません。テストの点数が良いことに満足するのではなく、将来の「生きる力」としてもっと幅広く成長していくことが大切です。 今回の記事では、学力が高いお子さんもさらに高みを目指して成長できる環境づくりについてご紹介します。ここでお伝えする内容は、学力に関係なく、どんなお子さんにも適した学習環境を整えるために役立つポイントをまとめています。ぜひ、すべての保護者の皆さまにお読みいただき、参考にしていただければ幸いです。 では、なぜ勉強が得意なお子さんの方が、力を伸ばすのが難しいと言われるのでしょうか?その理由をいくつか挙げてみます。
挑戦する機会が少なくなる
学力が高いお子さんは、日常的に困難な課題に直面する機会が少ないことがあります。周囲の大人が「もうできる」と思ってしまい、あまりチャレンジングな課題を与えない場合があります。また、本人も授業内容をすぐに理解できるため、それ以上学ぶ必要性を感じにくくなることがあります。結果として、学力が停滞し、自己成長が鈍くなってしまうこともあります。挑戦しない環境では、新たな知識やスキルを得る機会が減ってしまいます。
失敗を経験する機会が少ない
勉強が得意なお子さんは成功体験が多く、失敗する経験が少ないことがあります。そのため、失敗に対する耐性が低くなり、新しい挑戦を避けるようになることがあります。失敗を恐れて挑戦しないことが、成長の妨げになってしまうのです。日常的に失敗から学ぶ機会が少ないため、「試行錯誤」や「問題解決力」を発揮するチャンスが減ってしまうこともあります。
周りに成長を促す環境がない
学校の授業は、通常30人程度のクラスで行われます。同じカリキュラムをすべての生徒に向けて進めるため、平均的な学力を基準に授業が構成されています。そのため、学力が高いお子さんにとっては、授業が物足りなく感じられることがあります。「もっと学びたい」と感じても、それに応じる教材や課題が用意されていないこともあり、学習意欲が低下することにつながるかもしれません。 このように、すでに学力が高いお子さんでも、さらなる成長を目指すには、適切な学習環境を自ら整えていくことが必要です。では、どのような環境が効果的でしょうか?ここでは、そのポイントをいくつかご紹介します。
子どもの力を伸ばす学習環境 …
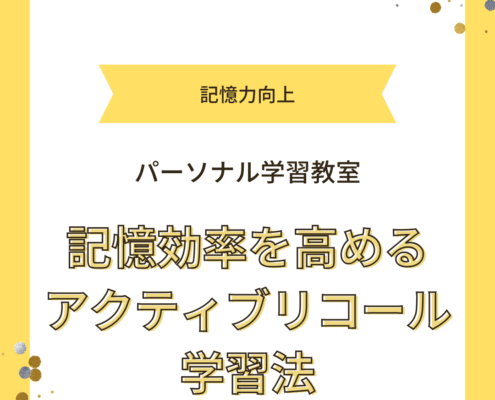
記憶効率を高めるアクティブリコール学習法
記憶効率を高めるアクティブリコール学習法
「何度練習しても覚えられない…」 「覚えるための勉強って退屈で、嫌になる…」 勉強において「記憶」や「暗記」は切り離せない要素です。応用力や活用力が重視される現代でも、その応用の土台となる知識をまず記憶しておかなければ始まりません。 たとえば、学校での勉強では「漢字や英単語を覚える」「社会や理科の用語を覚える」など、基本的な知識を身につけることが、多くの学びの出発点になります。しかし、この「覚える」という作業は、繰り返し読んだり書いたりと単調になりがちで、集中が続かなかったり、労力に見合った成果が出にくいことも。すると、勉強が「退屈でつまらないもの」に感じられ、学習意欲が減退してしまいます。 記憶や暗記の学習に工夫を凝らすことで、基礎的な知識の定着を助け、さらに学習意欲を高めることが可能です。今回は、効率よく学習内容を定着させる「アクティブリコール学習法」についてご紹介します。この学習法は、子どもから大人まで幅広く使えるので、ぜひ参考にしてみてください。
脳の記憶力を高めるメカニズム
効率の良い学習を実現するには、勉強時における脳の記憶メカニズムを理解しておくことが重要です。 インプットとは視覚や聴覚を通じて情報を脳に取り込むこと、具体的には「聞く」「読む」などの行為が該当します。一方で、アウトプットは脳に取り込んだ情報を引き出して使うことで、「話す」「書く」といった行為に当たります。 人は日常生活の中で多くの情報を見たり聞いたりして脳に取り込みますが、そのすべてを記憶するわけではなく、脳が「今後も使う必要がある」と判断した情報だけが記憶に残ります。 では、脳が「これは必要な情報だ」と判断するにはどうすればいいでしょうか?それには、「情報に繰り返し出会う」ことと「情報を実際に使う」という2つのステップが必要です。
情報に繰り返し出会う
例えば、通勤で歩く道で、見知らぬ人とすれ違った場合、1回きりの出会いであれば、その人の顔を覚えることはないでしょう。しかし、たとえ見知らぬ人であっても、毎日同じ時間に同じ場所ですれ違っていればどうでしょうか?「また会ったな」という経験が積み重なり、その人の顔を覚えるようになり、さらに「今日は表情が浮かないな」とその人を気に掛けるようになることもあるでしょう。 学習においても、情報に繰り返し出会うことは非常に重要で、これはインプットにあたります。繰り返し情報に触れることで、脳は「これは必要な情報なんだな」と判断し、記憶定着につながるのです。
情報を使う
人が勉強をする際、教科書を見て読んだり、講義を聞いたりするなどのインプットに頼りがちですが、インプットだけでは十分ではありません。インプットした情報を実際にアウトプット(書く・話す)して使うことで、脳に「この情報は必要なものだ」と認識させることが大切です。 インプットされた情報を繰り返し使うことにより、脳は「これは使う必要のある情報なんだな」と判断し、いつでも取り出しやすいように記憶を整理します。 このように、脳が記憶を定着させるプロセスには「情報と繰り返し出会う」ことと「情報を使う」経験が必要になります。 この2つのステップを踏まえた学習法がアクティブリコール学習法です。 いよいよ次からは、アクティブリコール法の具体的な学習方法をご紹介します。
効率的に記憶力を高めるアクティブリコール
アクティブリコールとは「自ら思い出す」ことを繰り返す学習法です。この方法でインプットとアウトプットをバランスよく行うと、脳に刺激を与え、記憶の定着が効率よく進みます。必要な道具は以下のとおりです。 …
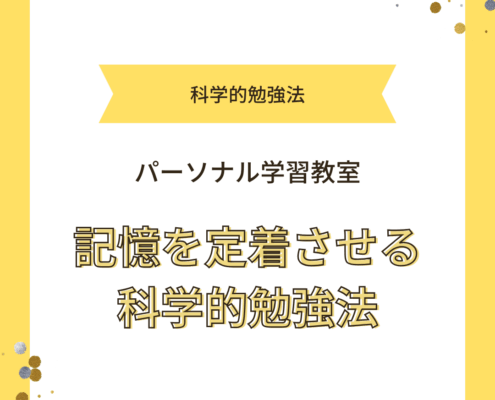
ただ努力するだけじゃダメ!記憶を定着させる科学的勉強法
「ただ努力するだけじゃダメ!記憶を定着させる科学的勉強法」
「たくさん勉強しているのに、成果が出ない…」 「繰り返し練習したのに、なかなか覚えられない…」 こんなふうに、一生懸命頑張ったのに思うような成果が得られず、やる気がなくなった経験はありませんか?自分の課題を克服しようと努力するのは素晴らしいことですが、もしその努力が実を結ばないと感じるなら、勉強法を見直すタイミングかもしれません。
よくある勉強法の落とし穴
学校では、たくさんの学習内容が教えられますが、「どう学ぶか」という勉強のやり方自体が教えられることは少ないです。そのため、受験生や社会人になると、どうしても自己流で勉強を続けてしまいがちです。しかし、効果的な方法で学ばないと、記憶の定着率が下がり、学習効率も低くなってしまいます。そこで今回は、科学的に裏付けられた、学んだことを確実に記憶に残すための効果的な勉強法をご紹介します。 まず、実はあまり効果が高くない、よくある勉強法について見ていきましょう。多くの人が「これが勉強だ」と信じている方法の中には、実は気合や根気に頼りすぎて、効率的に知識を吸収しにくいものもあります。そのデメリットを一緒に確認していきましょう。
①…
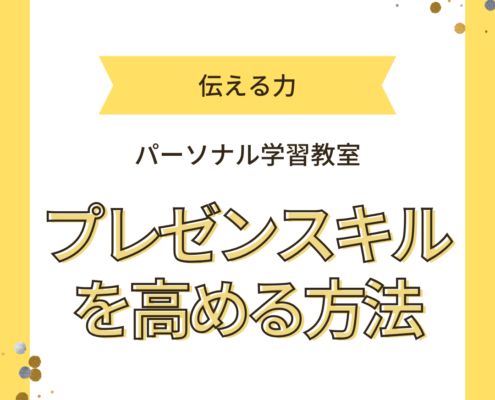
子どもの伝える力を育てる!プレゼンスキルを高める方法
子どもの伝える力を育てる!プレゼンスキルを高める方法
磐田市中泉で学童保育型学習塾プルートを運営している塾長の藤田です。
今回は「子どものプレゼンスキル」をテーマに考えていきます。 プレゼンテーションスキルは、現代社会において欠かせない能力の一つになっています。プレゼンテーションというと、お客さんの前で、営業マンが新商品についてアピールする絵をイメージするかもしれません。「小学生にも関係あるの?」と思われる方もいらっしゃることでしょう。実際には大いに関係あります!! 特に小学生のうちから発表したり、伝えたりする力を育むことで、自分の表現に自信を持ち、社会に出てからも自分の意見を伝えることができるようになるからです。子どもが学んだことを効果的に伝える力を育てるためには、テンプレートの活用とスモールステップの練習が必要です。今回は、伝える力でもあるプレゼンテーションスキルを向上させるためのポイントをご紹介します。
ポイント①:テンプレートを活用する
プレゼンをするには、まず話の組み立てが必要になりますよね。発表する機会を作ることの前に大事なのが、話の組み立てです。よくありがちなのが「自分の好きなモノ・コト」をテーマにみんなの前で話してみよう!と言って、とにかく発表する機会を作ってしまうことです。確かに経験を積むことも大切なのですが…。子どもは「好きに話して良いよ」と言われるとテーマにそって話せる子もいれば、どんどんテーマから逸れてしまって、何を話してるか収拾がつかなくなる子もいます。そうなると、聞いている子もよく分からなくなってしまい「〇〇ちゃんの発表は何を伝えたいのか分からなかった」という感想が出てきたりします。そうすると発表した子は「自分の発表はヘタなんだ」と思って、人前で話すことに対して苦手意識を持つことにつながってしまうんです。せっかくの子どもの「話したい」という気持ちを台無しにしてしまいます。 「話したい」、「伝えたい」という気持ちはそのままに、どのように話すかを決めてあげれば、発表もしやすくなります。そんな自分の伝えたいことを分かりやすく伝える魔法のようなテンプレートがあります。 それは「な・な・た・こ」と呼ばれるテンプレートです。「出典:10歳から知っておきたい魔法の伝え方…
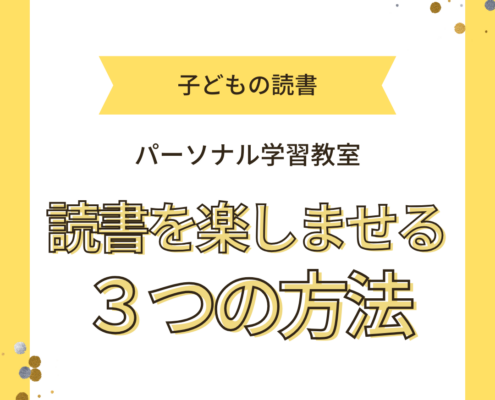
子どもに読書の楽しさを伝える3つの方法
子どもに読書の楽しさを伝える3つの方法
磐田市中泉で学童保育型学習塾プルートを運営している塾長の藤田です。 子どもが自然に「本を読むって楽しい!」と思って、進んで本を読んでくれたら、とても嬉しい気持ちになりますね。このように読書の楽しさや良さを知ってもらいたいと考える保護者の方も多いのではないでしょうか?
とはいえ、単に「本を読みなさい」だけで、読書に興味を持たせるのは難しいものです。そこで今回は、読書がより身近になり、楽しくなるための3つのポイントについてお伝えします。
ポイント①子どもと…
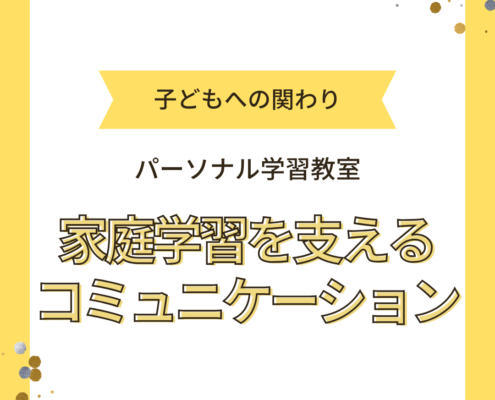
保護者の関わりがカギ!家庭学習を支えるコミュニケーション
保護者の関わりがカギ!家庭学習を支えるコ…
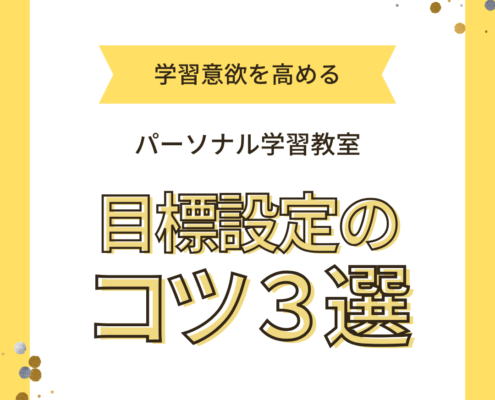
子どもの学習意欲を高める目標設定のコツ3選
子どもの学習意欲を高める目標設定のコツ3選
磐田市中泉で学童保育型学習塾プルートを運営している塾長の藤田です。今回は「子どもの自信につながる目標設定」について考えていきます。 学習への意欲を高めるために大切なのが「目標設定」です。具体的な目標をしっかりと設定し、実現に向けて行動することで、成果が見えやすくなり、達成感を味わうことができます。反対に「計画してもできなかった」という経験が子どもの中にできてしまうと、「目標を決めても無駄」、「計画なんて意味がない」という気持ちになってしまうかもしれません。一度挫折を味わってしまうと、なかなか前向きな気持ちになれませんよね。 そこで今回は、子どもが「やればできるんだ!」という自信を持てるようになるための目標設定のコツを3つご紹介します。取り入れられるものがあれば、ぜひ試してみてください!
ポイント①子ども自身が具体的で現実的な目標を立てる
目標を立てる上で重要なのは、具体的かつ実現可能なものであることです。 「成績を上げたい」や「勉強を頑張る」といった、ざっくりとした目標では、何をどう頑張るのかも漠然としてしまいます。 「次の算数のテストの点数を10点上げる」など、達成したかが明確に分かるように目標を設定します。 …
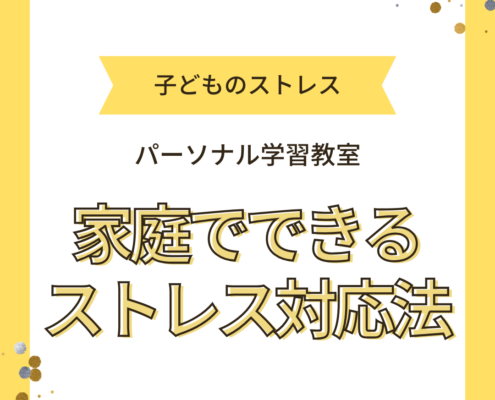
子どものストレスサインに気付いてる?家庭でできる対応
子どものストレスサインに気付いてる?家庭でできる対応
磐田市中泉で学童保育型学習塾プルートを運営している塾長の藤田です。
今回のテーマは「子どもが出すストレスサインと家庭でできる対応」についてです。 適度なストレスは子どもの成長に欠かせませんが、あまりに大きなストレスは心身にマイナスな影響を与えます。 「現代人はストレスが多すぎる」とよく言いますが、これは子どもも同じです。日常の様々な場面でストレスを感じていることがあります。子どもはそのストレスをうまく言語化できなかったり、発散できなかったりします。小さな心にいっぱいの不安や心配を抱え込んでいることも少なくありません。今回は子どもが出すストレスサインと家庭でできる対応方法をご紹介します。
ストレスの原因は?
ストレスの原因は様々です。新学期や引越しなど環境の変化によってストレスを感じることもあれば、学校生活や人間関係、習い事など日々の中で小さなストレスが積み重なって大きなストレスになることもあります。また原因は一つではなく、複数の要素が絡み合ってる場合もあるでしょう。 大人からしたら取るに足りないと思えることも、子どもにとっては大きなストレスの原因になることもあります。 さらに子ども自身がストレスを自覚できていないこともあります。意識的、無意識的かに関わらず、子どもはストレスを感じると、身体症状や行動の変化という形でサインを出します。それは子どもからの助けを求めるサインです。 ストレスサインにはどんなものがあるのでしょうか?
【子どものストレスサイン】
…